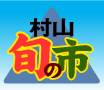山形県村山地域の農産物や直売所情報を紹介するサイトです
「村山旬の市」は山形県村山地域の農産物や直売所情報などを紹介するサイトです。
管内で生産されている旬の農産物、こだわり農産物の特徴や簡単な料理方法などを紹介しています。
また、村山の地域資源を活かした直売所、農家レストラン、農産加工品情報に、
イベントなどのおすすめ情報を加えて発信していきます。
ホーム > 旬の農作物なう!:さくらんぼ
さくらんぼ:人工受粉
2025.04.28掲載
山形県は全国のさくらんぼ生産量の約75%を占める、日本一のさくらんぼ産地です。「佐藤錦」をはじめ、様々な品種が栽培され、令和5年に500円玉サイズの大玉を誇る「やまがた紅王」が本格デビューしました。今年は県内にさくらんぼの苗木が導入されてから150周年の節目の年を迎えます。「やまがたフルーツ150周年」を記念して、さくらんぼ栽培について紹介します。
4月下旬に、寒河江市内でさくらんぼを栽培する株式会社「芳賀にこにこ農園」の芳賀孝博さん、あゆみさんの園地を訪れました。芳賀さんはさくらんぼ栽培の他、米、もも、りんご、花等、幅広く農作物の栽培をされています。
今回は、さくらんぼが実を結ぶために重要な「人工受粉」作業について取材しました。

① 芳賀さんのさくらんぼ畑です。「佐藤錦」や「紅秀峰」の樹が並びます。後ろに「やまがたフルーツ150周年」をPRするのぼりが見えます。

② 取材に伺った日は、「紅秀峰」が満開を迎える頃でした。さくらんぼは自分の花粉では結実することができないので、異なる品種の花粉をつけなければなりません。そのため、ハチや道具を使って受粉作業を行います。

③ 写真のような鳥の羽から作られた毛ばたきを使用して人工受粉を行います。毛ばたきは柄も含めると全長約2mもあります。
霜の被害に遭いやすい園地ですが、人工受粉を行うようになってから、安定して栽培ができるようになったそうです。

④ 受粉作業をしているあゆみさんです。開花した「佐藤錦」の花粉を毛ばたきにつけていきます。長い毛ばたきを使用して約3mの樹からも花粉を採取します。

⑤ 「佐藤錦」の花粉を採取した後は「紅秀峰」の樹に移動して、「紅秀峰」の花にやさしく触れるよう毛ばたきをくるくる回して、「佐藤錦」の花粉をつけます。花が咲いている時期は、毎日園地に足を運んで作業をするように心がけているそうです。

⑥ 芳賀さんが飼っているマメコバチの巣です。ヨシ筒の中にマメコバチが巣を作っています。さくらんぼの受粉作業は人工受粉の他、ハチの力を借りて効率的に行います。マメコバチの他、今年からミツバチも導入するそうです。

⑦ 白いバケツには花が咲いている受粉樹の枝を切って差しています。近くに受粉樹がなかったり、開花の時期がズレたりしても、ハチたちが受粉作業できるよう準備されていました。

⑧ 孝博さん(左)の話では、受粉作業と田んぼの作業が重なるので、毎年苦労されているそうです。しかし、高品質なさくらんぼを作るために頑張って受粉作業を行っていました。
作業の合間をぬって、マメコバチの巣作りに必要な採土場づくりも行っていました。来年活躍するマメコバチの子孫を残すための努力も欠かせません。
花が咲き終わりさくらんぼが実を結び始める頃に、芳賀さんは収量を予測するための独自の取組をされているそうです。次回はその取組と「摘果」作業について、取材する予定です。
さくらんぼ:着果調査・摘果
2025.06.05掲載
5月上旬に「着果調査」、5月下旬に「摘果」作業の様子を取材しました。

① 着果調査を行っている芳賀あゆみさんです。「株式会社芳賀にこにこ農園」では、2021年の不作を受け、この調査を本格的に行うようになりました。
調査では、着果数と果実の大きさを測ります。調査結果は、その後の作業計画を立てる際の参考とするそうです。

② 着果している果実(白矢印のように大きくなっている果実)の数を数えていきます。園地を歩きながら複数の樹でランダムに枝を選び、調査を行います。

③ 着果した果実の大きさをノギスで測ります。こちらも着果数同様に、ランダムに調査します。
「紅秀峰」では、「満開14日後に、果実径が約7mm以上の果実が結実しやすい」という県の研究結果を参考にして、調査をしているようです。取材日は、満開17日後ということもあり、写真の果実は11.1mmまで大きくなっていました。

④ その他、果実の写真も撮り、芳賀さんはデータを全て営農支援ツール「アグリノート」に記録しています。過去のデータと比較をし、収量・販売の見込み数を算出しています。
データを家族で確認しながら、今年の予約数をどのくらいに設定するか、摘果や収穫時の人の手配をどうするか等を相談していくそうです。

⑤ 続いて、摘果作業です。大玉で糖度の高い果実を生産するために、着きすぎた果実を摘み取る作業です。芳賀さんは、JAの「さくらんぼ便り」や普及課の実践者セミナーを受講し、それらを参考にしながら作業に取り組んでいます。

⑥ 枝あたりの果実数が2~3個くらいになるように、余分な果実を摘み取ります。左下の楕円内にあるような、双子果も見つけ次第、摘み取ります。

⑦ 丸で囲んだような小さな果実は、自然に落果するため、こちらは摘み取らず、効率よく摘果作業が進むように心がけています。

⑧ 摘果の作業は田植えの時期と重なることから、夫の孝博さんは田植えに、あゆみさんは摘果に専念して作業に取り組んでいます。近年、さくらんぼの栽培は高温や異常気象に悩まされていると話していました。
日本一のさくらんぼ産地を支える生産者は、大玉で品質の良いさくらんぼを生産するために、たゆまぬ努力をされていることが、今回の取材でわかりました。
次回は、いよいよ「収穫」作業です。芳賀さんは果実の大きさが500円玉サイズを誇る「やまがた紅王」の栽培もされています。「やまがた紅王」を含め、さくらんぼの収穫や箱詰め作業等を紹介します。
さくらんぼ:収穫・選果・箱詰め
2025.06.30掲載
6月中旬、「株式会社芳賀にこにこ農園」の園地でさくらんぼの収穫と選果(果実の選別)、箱詰めの様子を取材しました。
前回取材した摘果作業から現在にかけては、ハウスのビニールかけや、果実への日当たりを良くするために新しい枝の一部を切り落とす摘芯(てきしん)作業などが行われていました。

① 待ちに待った収穫です!
ハウスには実割れを防ぐビニールがかけられ、摘果時には目立たなかった果実も赤く色づき、大きく成長しています。
さくらんぼの収穫作業は早朝5時からスタートし、ピーク時は5時~7時に8~9人が参加します。常連の方々に加え、1日農業バイトアプリ「daywork」で募集した短期スタッフも多くいます。会社員の方は収穫作業後、そのまま出勤されるそうです。

② 取材日は「佐藤錦」の収穫が行われていました。収穫作業は脚立を使って行うため、転落事故や熱中症を起こさないよう、芳賀さんは作業員の健康管理を常に気にかけています。園地には、作業者全員に熱中症対策を周知するための看板を設置する等、工夫をしています。

③ 芳賀さんの園地では、通常、1本の樹についた果実をすべて収穫する「がらもぎ」を行います。今年は「佐藤錦」の着色のバラつきが大きいため、適期に熟した果実だけを選んで収穫する「すぐりもぎ」を行っています。
写真の銀色の反射シートは、着色を促進するための工夫の一つです。

④ 収穫をしている芳賀孝博さんです。
今年は収穫期の気温が高いので、生育状況を見て、反射シートの設置や収穫する園地を決定しているそうです。
「実った果実は全て収穫し、できるだけ多くの人に食べてほしい。お客様の注文には全力で応えたい。」と話していました。

⑤ 芳賀さんの園地では「佐藤錦」の他に、「紅秀峰」や大玉品種の「やまがた紅王」も栽培しています。
「やまがた紅王」はまだ若木のため販売していませんが、今回は特別に樹を見せていただきました(手に持っているのが「佐藤錦」、右が「やまがた紅王」です)。
芳賀さんは「やまがた紅王」の樹の成長を楽しみにしていました。芳賀さんの園地でのさくらんぼの収穫作業は、6月末頃まで続きます。

⑥ 収穫した果実は作業小屋に運ばれ、選果した後に箱詰めをします。選果・箱詰めは9時から作業を開始し、忙しい時期は午後4時~5時頃まで行います。
ここでも常連スタッフと「daywork」で募集したアルバイトが作業を行っています。通常7~8人、忙しい時期は20人ほどで作業しています。

⑦ 割れた実等が混入しないよう細心の注意を払いながら、選果・箱詰めを進めていきます。
複数のスタッフで作業するため、どの作業員が詰めても均一な品質になるよう声を掛け合っています。

⑧ 箱詰めは贈答用やパック用など詰め方が異なるため、詳細な資料を準備しています。
作業前に全員で箱の規格や作業手順を共有します。初めての作業者には、見本写真で注意点を分かりやすく説明します。県の出荷基準資料も参考にしながら着色状況や品質基準を確認しています。

⑨ 箱詰めの完成品についても、着色や詰め方にバラつきが出ないよう、スタッフがお互いに仕上がりを確認しながら作業しています。

⑩ 贈答用の箱詰め作業をしている芳賀あゆみさんです。「お客様の注文に確実に応えるため、収穫時期は気が抜けない。」と話します。「芳賀にこにこ農園」では、収穫・選果作業の負担軽減のため、選果の簡易化や配達日時指定をあまり受けないなどの工夫もされています。
また、生産者が年々減少していることを残念に思い、「自分たちの取組で、生産者も消費者もみんながハッピーになれるよう頑張りたい。」という言葉が印象的でした。
さくらんぼの「収穫・選果・箱詰め」作業を取材し、自分が作ったさくらんぼを1つでも多く、お客様のもとへ届けるために、生産者が込める思いと努力を間近で感じることができました。
収穫が終わっても、ハウスのビニールの片づけや草刈り、防除、お礼肥えの施用など、さくらんぼ作りの作業は続きます。
次回は冬に、おいしいさくらんぼを生産するための「剪定」作業の取材を予定しています。
さくらんぼ:剪定
2026.01.21掲載
12月中旬、芳賀さんのさくらんぼ園地に剪定作業の取材に伺いました。芳賀さんは米の作業がひと段落し、ようやく果樹の剪定作業に向かうことができるとのことでした。

① 今年は現段階では雪がなく、安心して作業が進められる状況です。
例年1月くらいから本格的に剪定作業を開始するとのことですが、さくらんぼ以外の樹種もあるので、今年は雪がないうちに、急いで作業を進めていきたいと話していました。

② 「佐藤錦」の花芽の様子です。収穫後の病害虫防除や夏季管理のおかげで、健全な花芽がついていました。

③ 取材日は「佐藤錦」の剪定作業中でした。樹齢約10年とのことで、まだ枝が多い樹なので、将来、樹の骨格となる大事な枝を見極め、大事な枝を邪魔する枝を間引くことから始めるそうです。

④ 樹全体の日当たりや風通し、樹勢のバランスを考えながら、樹上部の太い枝を徐々に切り詰めていきます。その際、一気に太い枝を切り落とすと、樹勢を乱してしまうため、2~3年後を見据えて切るのが難しいと話していました。

⑤ 例年、霜害に遭いやすい園地のため、霜に当たりやすい目線から下の枝は、将来を見据え徐々に無くすように考えて、剪定しているとのことです。また、成り枝(果樹を成らせる枝)として残す枝も考慮しながら、剪定を進めます。

⑥ のこぎりで切除した大きい枝の切り口には、病害を防ぐために塗布剤(人間でいうとばんそうこうの役割を果たす薬剤)を塗り、切り口から病気が入るのを防ぎます。

⑦ 芳賀さんは収穫時の作業性と収量の確保を見通しながら、はさみを用いて成り枝を整理していきます。

⑧ 剪定後の「佐藤錦」の樹です。剪定前と比べて、枝と枝の重なりが解消し、すっきりしました!
「株式会社芳賀にこにこ農園」では、剪定作業は孝博さんとお父さんのお二人で作業をしているとのことでした。雪が降ったら園地の除雪をしながら、剪定作業は3月中頃まで続くそうです。芳賀さんの園地では、今年、「佐藤錦」を伐採し、高温に強い「紅秀峰」や「やまがた紅王」の改植を行いました。若木が増えた分、収量は少なくなりますが、お客様の声にお応えできるように、おいしいさくらんぼを出荷したいと話してくださいました。
今回がさくらんぼの取材の最終回となります。お忙しい中、取材に御協力くださった「株式会社芳賀にこにこ農園」の芳賀孝博さん、あゆみさん、本当にありがとうございました。